- 18
- 3.66
「静かな退職」--アメリカのキャリアコーチが発信し始めた「Quiet Quitting」の和訳で、企業を辞めるつもりはないものの、出世を目指してがむしゃらに働きはせず、最低限やるべき業務をやるだけの状態である。 「働いてはいるけれど、積極的に仕事の意義を見出していない」のだから、退職と同じという意味で「静かな退職」なのだ。 ・言われた仕事はやるが、会社への過剰な奉仕はしたくない。 ・社内の面倒くさい付き合いは可能な限り断る。 ・上司や顧客の不合理な要望は受け入れない。 ・残業は最小限にとどめ、有給休暇もしっかり取る。 こんな社員に対して、旧来の働き方に慣れたミドルは納得がいかず、軋轢が増えていると言われる。会社へのエンゲージメントが下がれば、生産性が下がり、会社としての目標数値の達成もおぼつかなくなるから当然である。 そこで著者は、「静かな退職」が生まれた社会の構造変化を解説するとともに、管理職、企業側はどのように対処すればよいのかを述べる。また「静かな退職」を選択したビジネスパーソンの行動指針、収入を含めたライフプランを提案する。
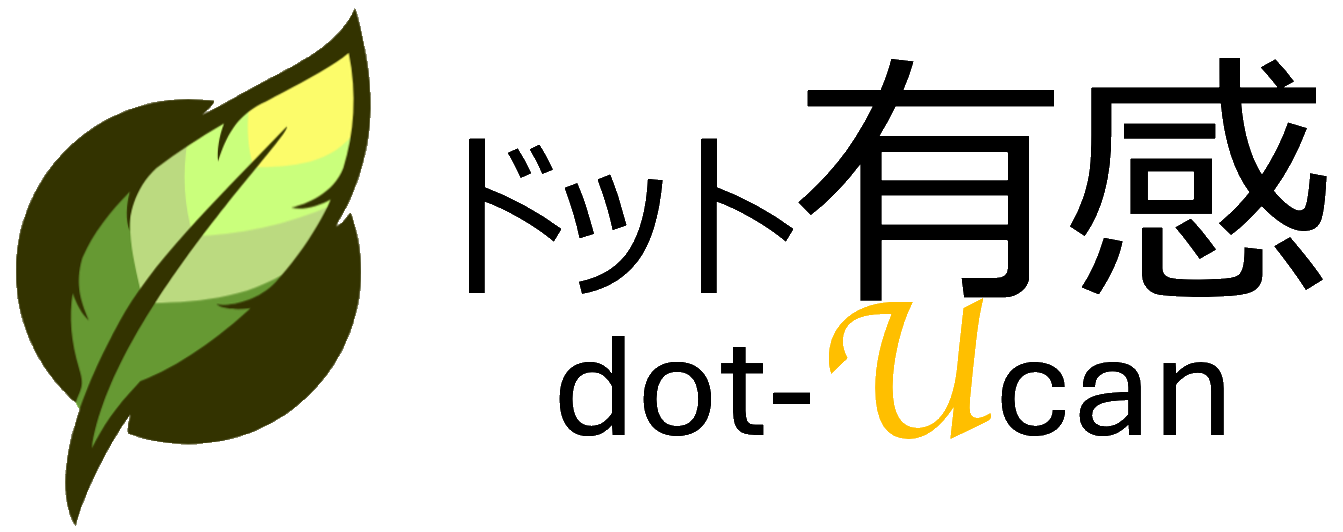
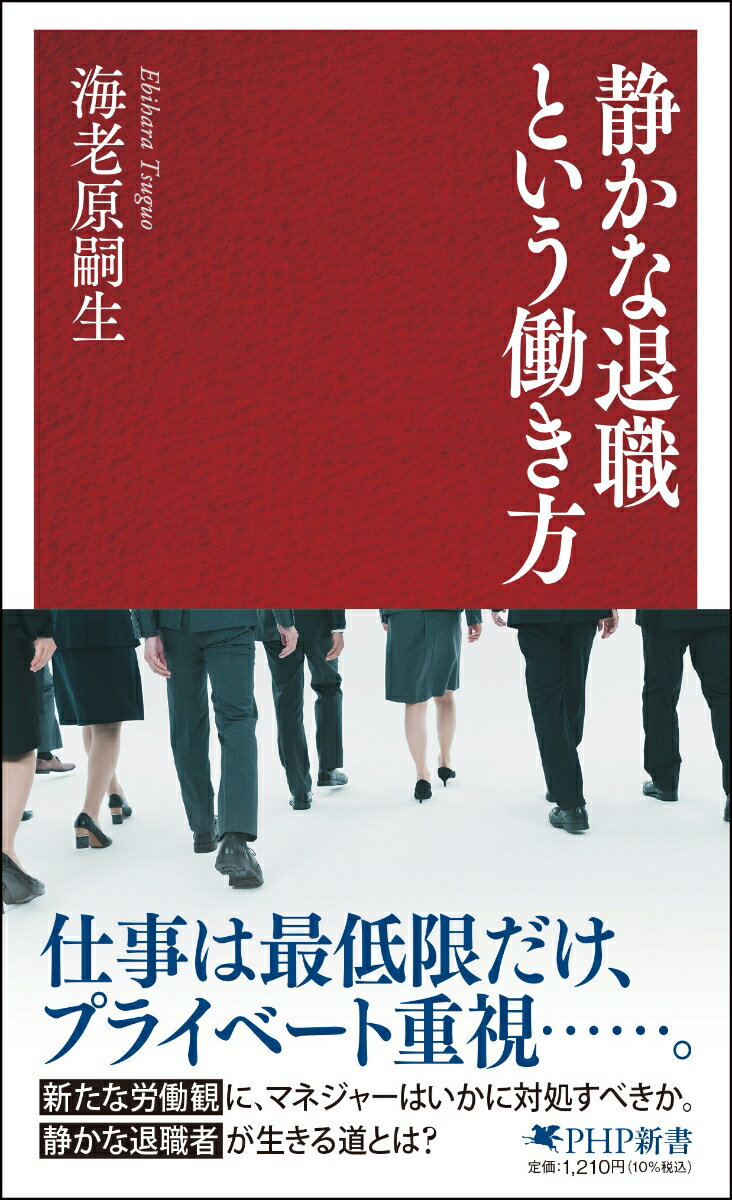
レビュー(18件)
対応の具体策が難しいですね
本の内容は自分自身も理解していた内容ですが、受けとめる方の意識の転換は具体的には非常に難しいと認識、その指導・教育を熟慮します。
社内の面倒くさい付き合いは可能な限り断る。 上司や顧客の不合理な要望は受け入れない。 残業は最小限にとどめ、有給休暇もしっかり取る。 それは大いに同感だが、 異動するたびに1つ長く付き合える顧客を増やしていく。 重要顧客1社、厄介な顧客1社、仲良し1社に全力投球。 って、いやいやいや。 後半部分は大いに不満であった。
静かな退職者として生き残る方法がわかる。キャリアアップできない海外の事情もなんだか極端だし、日本の生産性に結びつかない労働時間もよろしくないし、今後の働き方はこうなるんじゃないかなと思う。静かな退職に誰もが納得できる理由なんかなくていい。家庭の事情があろうとなかろうと、それなりの働き方があるといいよね。選択肢があることが救いになりそう。静かに退職しながら副業したい。