- 64
- 4.03
この本は、これまで1万人以上の発達障害の人や精神疾患の人たちと向き合ってきた精神科医の著者が、発達障害の特性を持つ人、とりわけADHDとASDの人が“見ている世界”を紹介する一冊です。 発達障害とは、一言で言えば脳機能の特性。状況を読んだり、人の気持ちを推測したりする脳の働きが定型発達の人より弱いことがわかっています。 失礼なことを平気で言ったり、 繰り返し約束を破ったり遅刻したり、 すぐに泣いたり怒ったり、 じっとしていられなかったり… 理解に苦しむその言動も、本人たちが物事をどう受け止め、感じているのか、つまり“見ている世界”を理解し、その対応策を学ぶことで、ともに生きるのが楽になるはずです。 たとえば、「発達障害の人には社交辞令や皮肉が通じない」といいう困りごとの場合、その理由が「脳の特性により、言葉を字義通りに受け取ってしまう」という原因によるものだと知れば、少しは気持ちが落ち着くでしょう。 そして、「発達障害の人と話すときは、極力ストレートな表現を心掛ける」という対処法にも納得がいくはずです。 この本では、大人から子どもまで、そんな身近にある困りごとを32個紹介し、その理由と対応策を紹介しています。 「自分も発達障害かも?」と思う人も、生きづらさの正体を知ることで適切にサポートを受けたり、対応策をとったりしていくことで、困りごとが解決されていくことでしょう。 特性を持つ子どもの親御様も、子育てが少し楽になるはずです。 定型発達の人でも、発達障害の特性に似た傾向を持つ人は、決して少なくありません。 また、発達障害との診断はくだらなくとも、発達障害の特性を持つ“グレーゾーン”の人もいます。 発達障害なのか。 グレーゾーンなのか。 定型発達なのか。 そういった診断的な面だけにこだわらず、さまざまなコミュニケーションの困りごとを解決するツールとしてこの本がお役に立てれば、これほどうれしいことはありません。
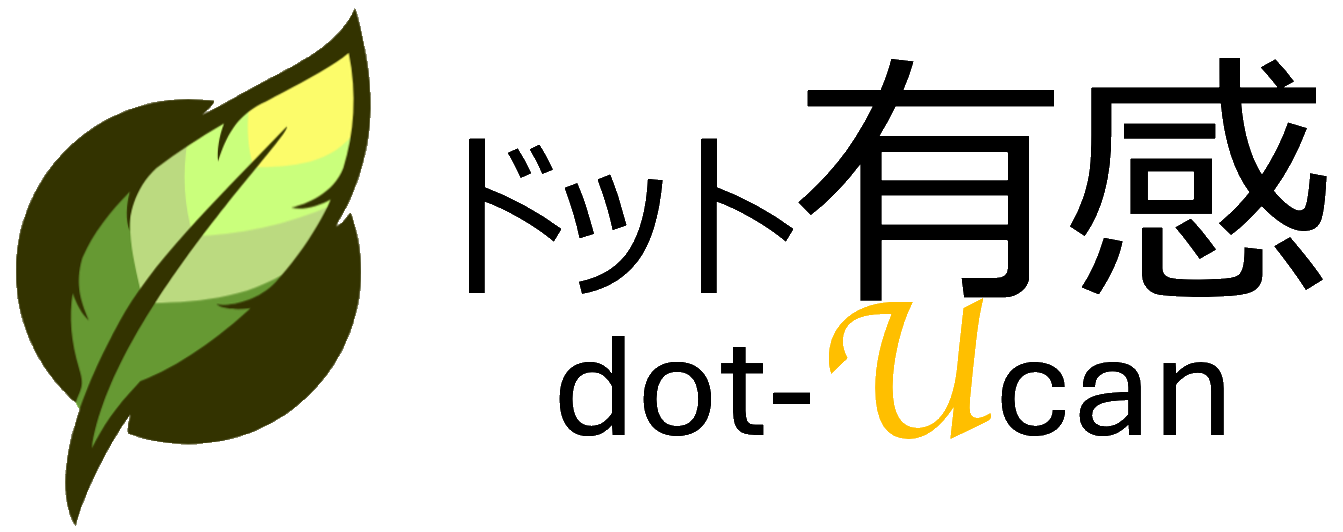
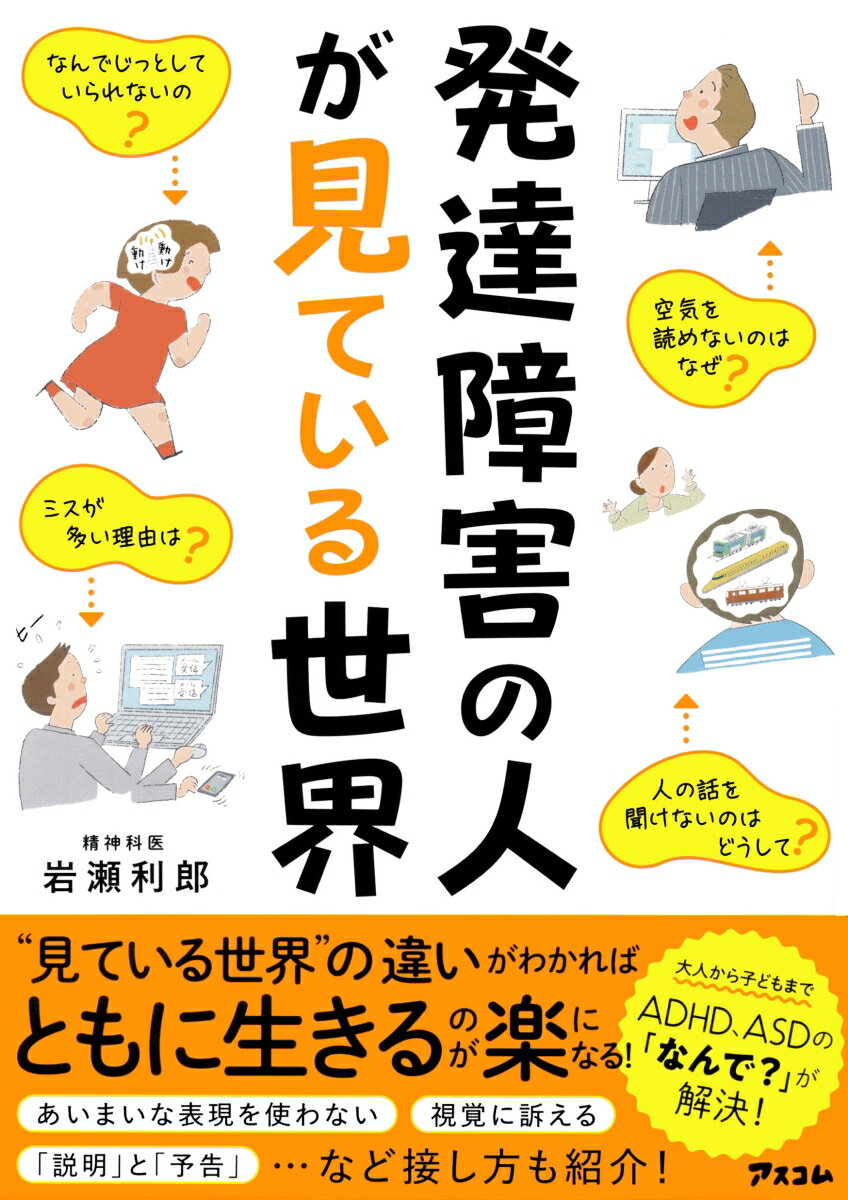
レビュー(64件)
わかりやすいです。色々と調べてみたくなり他の本も読み始めました。
発達障害の人の気持ちが、今まで以上に分かりました。
分かりやすい
以前の仕事がら、興味のある本です。また、回りにも気になる人がいて、お付き合いをするなかで、お互いに嫌な思いを回避するための参考になればと思いました。分かりやすい内容で、読みやすく、今後の人付き合いに役に立つと思っています。 また、自分のためにも考え方を変える材料になりそうです。 少し繊細すぎるところがあったり、他の面でも気にしていることがあるので、「なるほど~」と思えるところがあります。 何度か読み返して、理解し今後に役立てていきたいです。
入門としてはいいのかもしれないが
発達障害を全く知らない人向けの内容でした。 入門としては良いのかもしれませんが。
わが子は発達障害でしたが、子育てをしているときにこのような本があったらうまく対応してあげられたのになあと思いました。そんなとき身内の子も発達障害と分かったのでこの本をプレゼントしました。