- 105
- 4.34
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 【精神科医・松本俊彦氏 推薦!】 (『誰がために医師はいるーークスリとヒトの現代論』著者) 「殴ってもわからない奴はもっと強く殴ればよい?--まさか。 それは叱る側が抱える心の病、〈叱る依存〉だ。 なぜ厳罰政策が再犯率を高めるのか、 なぜ『ダメ。ゼッタイ。』がダメなのか、 本書を読めばその理由がよくわかる」 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 叱らずにいられないのにはわけがある。 「叱る」には依存性があり、エスカレートしていくーーその理由は、脳の「報酬系回路」にあった! 児童虐待、体罰、DV、パワハラ、理不尽な校則、加熱するバッシング報道……。 人は「叱りたい」欲求とどう向き合えばいいのか? ●きつく叱られた経験がないと打たれ弱くなる ●理不尽を我慢することで忍耐強くなる ●苦しまないと、人は成長しない……そう思っている人は要注意。 「叱る」には効果がないってホント? 子ども、生徒、部下など、誰かを育てる立場にいる人は必読! つい叱っては反省し、でもまた叱ってしまうと悩む、あなたへの処方箋。
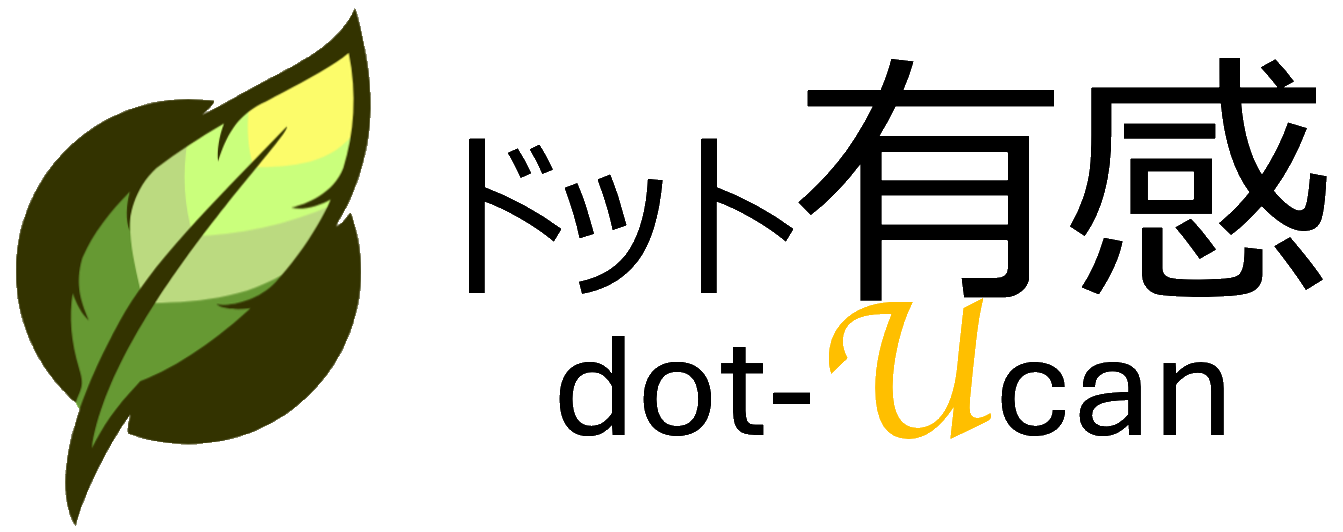
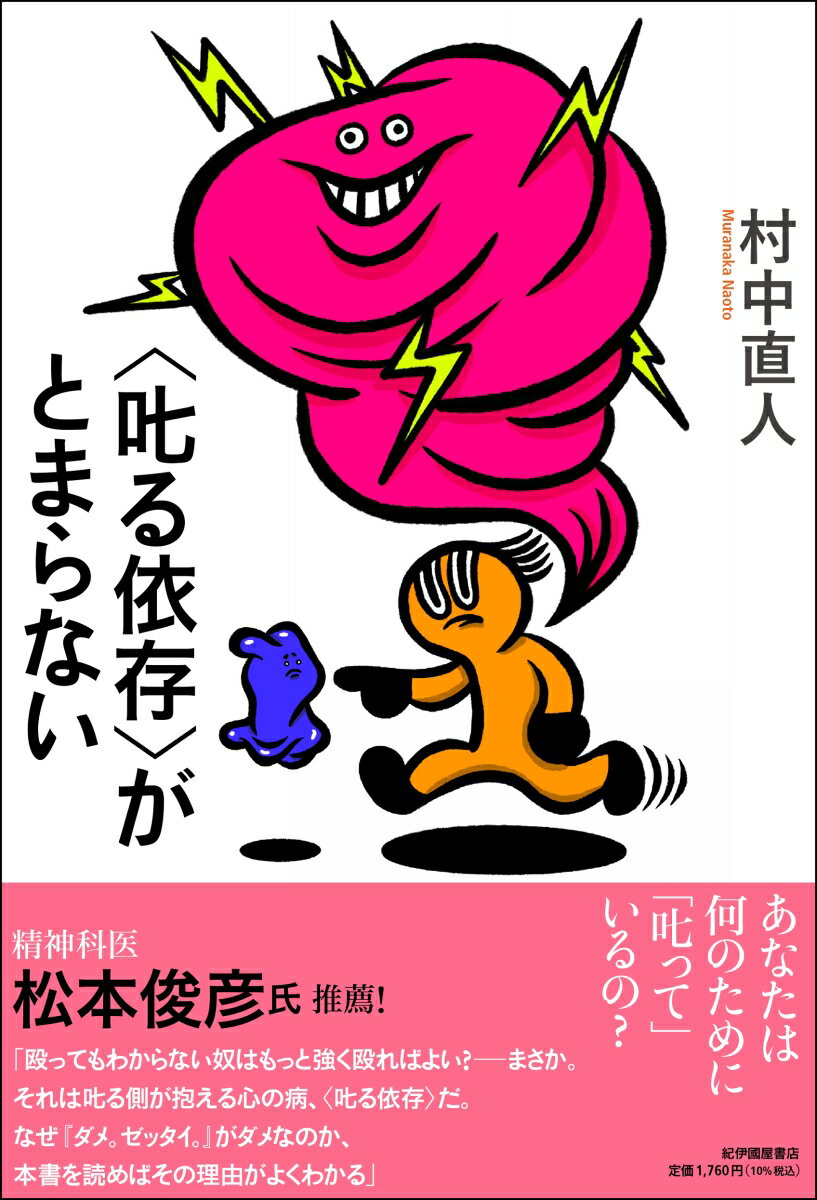
レビュー(105件)
子育ての中で怒ってばっかりで、このままでいいんだろうか?と思いこの本を手に取りました。 脳科学の観点から「叱る」行為を分析されており、気づきも多く、とても興味深い本でした!
自分が子供に叱ってしまうメカニズム。わかっていたつもりでも理解できていない部分はたくさんありました。勉強になりました。
とても面白いと思います、子育てに役立つこと間違いないですね。
認識を改められた本。何のために叱るのか?叱る方は、指導と思っていることもその効果は限定的。学びや成長につながらず、その場からの逃げにしかならないという指摘は重い。また叱る方こそ、快感になっている、正当化する原理が働くというのもわかる。「私はそうやって強くなった」と言う生存者バイアスを持っている人は多いなあと感じた。叱られることによる「学習的無力感」は本当にそうだと納得。またやりたいということを持つことまたやるということが育まなければいけない能力という視点は私自身も欠落していた。自己効力感はやはり重要だ。
叱るを手放す
最近子どもを叱りすぎだなと思い、この本を読んでみました。まさに私は叱ることに依存してたんだと気付かされました。我が子が1人でできるようにならないと、時間内に出来るようにならないと小学校で困ると勝手に不安になって焦っていた気がします。まだ我が子はその段階にはいなかったのだと思いました。叱るを意識して手放していけるよう頑張ります。とりあえず今日の夕方は一度も叱らず、久しぶりに穏やかな時間を過ごせました。