- 14
- 4.85
苦手や「困った」を遊びで減らそう! 診断名がついているわけではないのに、学校で小さなトラブルが発生してしまうわが子の言動の背景になる「問題」について、療育プログラムが人気で、予約のとれない作業療法士、木村順さんがわかりやすく解説し、子どもの「困った」のタイプ別に、親子遊びをバリエーション豊かに紹介します。 教室で椅子をガタガタさせて、落ち着きがない、板書についていけない、先生の注意を聞けない、友達とうまくコミュニケーションができない…そんな子ども達の「困った」を減らしてあげましょう。 子どもの成長に伴って改善していくことの多い小さなトラブルですが、親が追い詰められてしまわないよう、先生や友達など、周囲の理解を得るために、先輩ママたちが実践してきたことや、木村順さんが療育指導の中で保護者にアドバイスしていることをまとめた1章を作りました。 【編集担当からのおすすめ情報】 この遊びをすると、どういう力が育ち、その結果、学校でのわが子はどのように変わるのか、ということを、遊び方ごとに解説しています。 板書についていけない子どもには、目の動きを改善する運動をさせてあげると、行の読み飛ばしがなくなったり、字も読みやすくなったりします。友達とトラブルを繰り返してしまう子には、実際にあったトラブルをテーマにした、3択クイズを出してあげると、対応が学べます。 親子とも楽しめる遊びばかりなので、すぐに始められます。
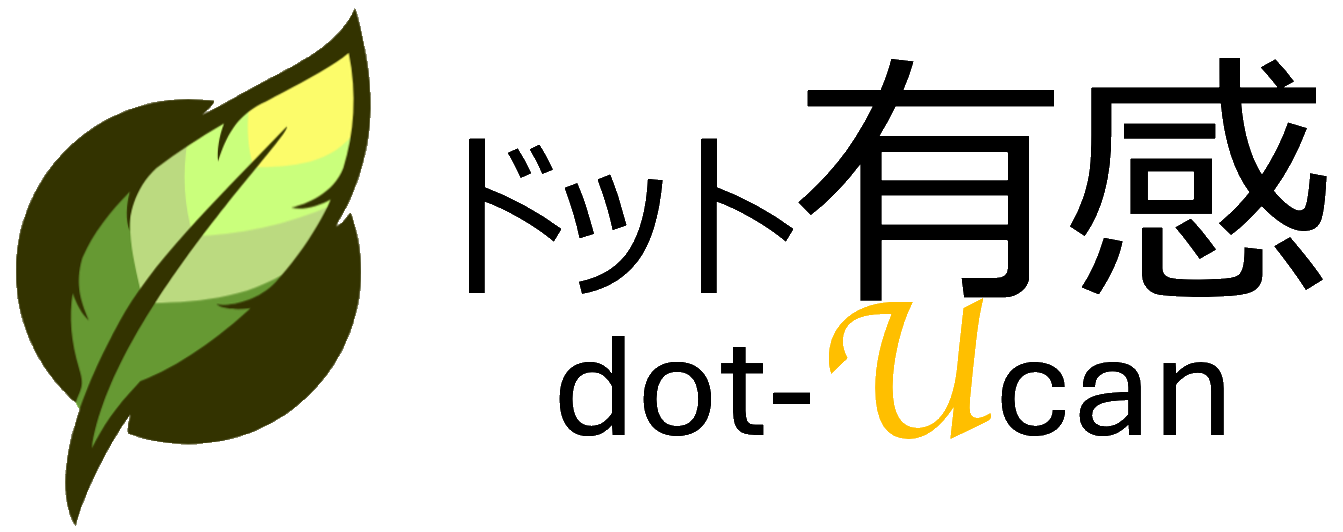
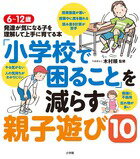
レビュー(14件)
来年入学式 もっとはやくこの本に出会いたかった!!
これはかなりおすすめです
幼稚園の担任に多動ぎみであること、指示が入りにくい事などを指摘された年長の娘。 地域の発達相談や発達外来にも行き、wiskをやりましたが確かにバランスがやや悪いけど…と確定にはならず。しかし、ADHDに当てはまる事がとても多いのでどうしたら良いものか、来年度から小学校だけど本人が困ったり悲しい思いをしたらと思っていました。 コロナの影響もありますが年齢やそこまできつい症状がないというところから療育には通えず。 しかし、このままでは絶対に小学校で躓きが起こり、親が「何かしておけば…」と後悔する可能性が高いので本を何冊か買ってこちらも購入してみました。 この本には4人の子供が出てきますがAちゃんがドンピシャ、まるでうちの娘のようでかなり問題点やどうしてこんな行動を?という疑問がかなり分かりやすかったです。 小学校で起こりそうな問題を先回りして予習できた気分でした。これからトレーニングをして楽しく備えたいと思います。 【眼球の動き】がかなりなるほど!!と思いました。 診断が下りてない子でも、なんとなく落ち着きがない?空気が読めない?と思う部分があるなら保護者に読んでみて欲しいです。
早速実績
発達障害の子供のあるある。 実践して効果が出るか期待。時間はかかるだろうけど地道に親子でやっていきた。
何度も見て遊びを確認しています
絵が多く分かりやすい。取り組んでみようと思う遊びがたくさん書かれています。
療育で作業療法士さんにすすめられて買いました。トランポリンは家にありましたが、漫然と飛ぶだけだったので、色々遊びを取り入れながらやっていきます。