- 77
- 3.56
●仕事に不適応な新人社員 注意されるとすぐに落ち込んでしまう新人。場合によっては翌日から仕事に来られなくなるケースも。一方で、注意に反発し、仕事の改善が見られないケースなども発生。どうやって接すればいいのか、悩む上司なども大量に発生している。 新入社員になる以前に、小学校の現場では、暴力事件が急増中。子ども同士のコミュニケーションも変調を来しているのだ。中学受験を目指すなどの早期教育は効果はあるが、その効果は一時的なもので、長期的には意味がないことが多い。さらには、親といる時間が長く、友達と遊んだり、自然と触れ合ったり、いろいろ冒険したりして、主体性や多様性を身に付ける機会が減っている。ひとりになるとゲームに集中することもたびたび。 本書では、本来身に付けるべき子どもの教育について、親の立場、会社で指導する立場から見る。 ●自己コントロールなどの「非認知能力」が求められる 2000年にノーベル経済学賞を受賞したヘックマンも、40年にわたる研究で、早期教育が知的能力を高める効果については認めている。しかし、それだけが学歴や収入という成功に結びついたわけではないと結論づける。現に認知能力(知的能力)に関しては、8歳の時点で効果は失われている。だが、成人後のデータを見ると、早期教育を受けたものの方が、学歴も年収も高くなっていた。協調性、忍耐力、やる気などの非認知能力がその後の成功のカギを握る。 そのためには子どもへの結論を急がない。ひたすら待つ、一緒に考えるという姿勢も必要になるのだ。 子育てについては多くの本が出ているが、本書は心理学や教育学の最新の知見から語るので説得力がある。本書は、『ほめると子どもはダメになる』(新潮新書)の第2弾ともいえる内容で、子どもの忍耐力や協調性、自立性の必要性を強く説く。子育て(特に小学生)に悩む親世代にとっては、必読の一冊です。 プロローグ 第1章 「頑張れない」「我慢できない」--今の子ども時代に足りないもの 第2章 早期教育に走る親たちーー果たして効果はあるのか 第3章 幼児期の経験が将来の学歴や収入を決める? 第4章 子ども時代に非認知能力の基礎をつくっておく 第5章 子ども時代の習慣形成でレジリエンスを高める
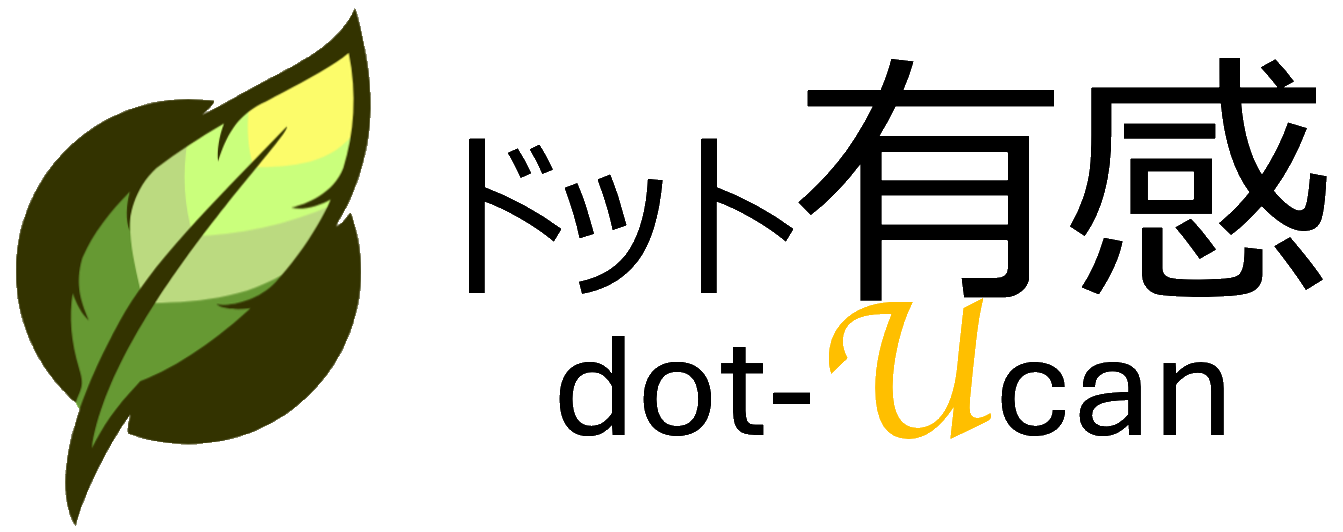
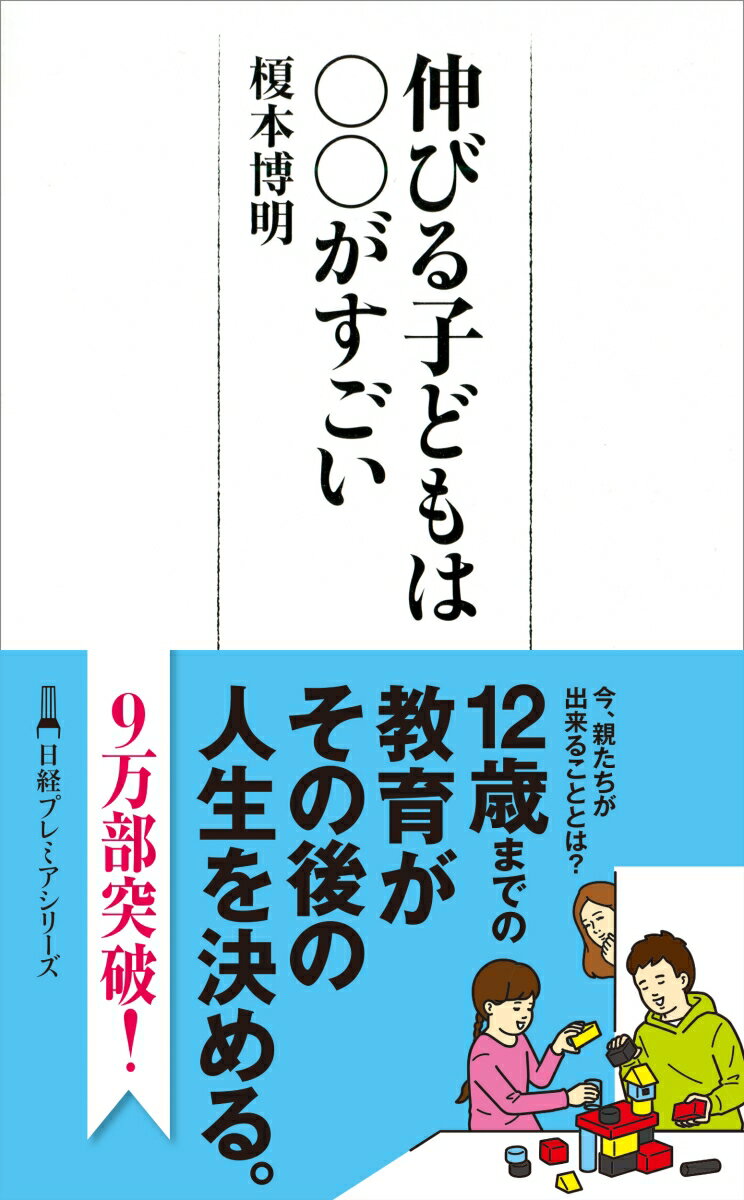
レビュー(77件)
買う必要なし
要旨としては、 「我慢のできない若者が最近増えているのは、最近流行の「叱らずにほめて伸ばそう」とする教育が元凶だ。昔のように子どもにしっかり叱って忍耐力をつけることが大事だ。私も幼少期に大人からよく叱られて成長したものだ。」 そもそも筆者は、自身が今流行りと述べる「ほめる教育」の意味を理解していない。今巷に多く溢れるそれらの本は、非認知能力を伸ばすための意義あるほめ方について述べられているのである。そして、ただ注意すべきことを放置し叱らないべきと謳ったものではないはずだ。 かつての教育で育った日本人が我慢強かった、忍耐力という非認知能力が高かったと述べたいのだろうが、社会全体の停滞感や現状を踏まえ、元来の教育ではいけないという舵取りがなされた背景を、筆者は理解できていないではないか。 筆者の生きてきた昭和とは異なり、時は令和。「これさえやっていれば」という明確な指針がなく、自分が進むべき方向を自分で考え切り拓いていく必要がある。創造力が問われる時代。 文中で欧米やアメリカをやたらと批判するが、世界比較での日本の自殺率の高さ、幸福度の低さは、果たして筆者はどう捉えているのだろうか。 親が切に望む同一の願いは、我が子の幸せである。ただ幸せに生きてほしい、そのためにはどうしたらいいのか。 そういった思いで試行錯誤され、日々の子育てに励んでいる親御さんたちが、どうかこの本を手にされ自信を失われることがないようにと思い、普段全くレビューをしないのですが、どうしても伝えたいと思い投稿しました。 ただ一部、幼児期から英会話や早期教育を受けさせることよりも、遊びを通じて非認知能力を高めることが重要という点については同意。 (それも学者的な学術的研究結果を踏まえてではなく、他者コメントを引用しているだけの部分ですが。そして筆者の非認知能力の認識もずれているように見受けられます。)
とっても、勉強になりました!これからの参考とします。