- 6
- 3.83
年々受験者数が増加する小学校受験。 かつてはごく一部の人しか知らない世界と思われてきたが、共働き世帯の参入が進み、中学受験ほどではないが盛り上がりを見せつつある。 その理由として、コロナ禍で私立の方が公立よりも対応がスピーディであったことや、中学受験の過熱や大学入試改革などを踏まえて早期に進路を決めてしまいたいというニーズもあると思われる。 ただ、どういう子どもが小学校受験に向いているのか、家庭でどういうことができるのかというと、まだノウハウが知れ渡っているとはいえず、一部のインナーサークル内で情報が流通している印象が強いのではないだろうか。書籍の多くも塾関係者のものであり、塾への誘導のために、根幹にかかわる部分は避けて記述しているのが実情である。 しかし、何となく興味を持つ人も増えている中で、とりあえず小学校受験とはどのようなもので、受かるにはどうすればいいのか、知りたい人が増えていると思われる。 そこで本書では、私立小学校に長年勤務した著者が、「どういう子どもに入学してほしいか」「そういう子どもをどうやって育てたらよいか」ということを解説する。 小学校受験初心者がこれからどういう考え方で、どういう取り組みをしていけばよいかを伝える。家庭でできる入門書。
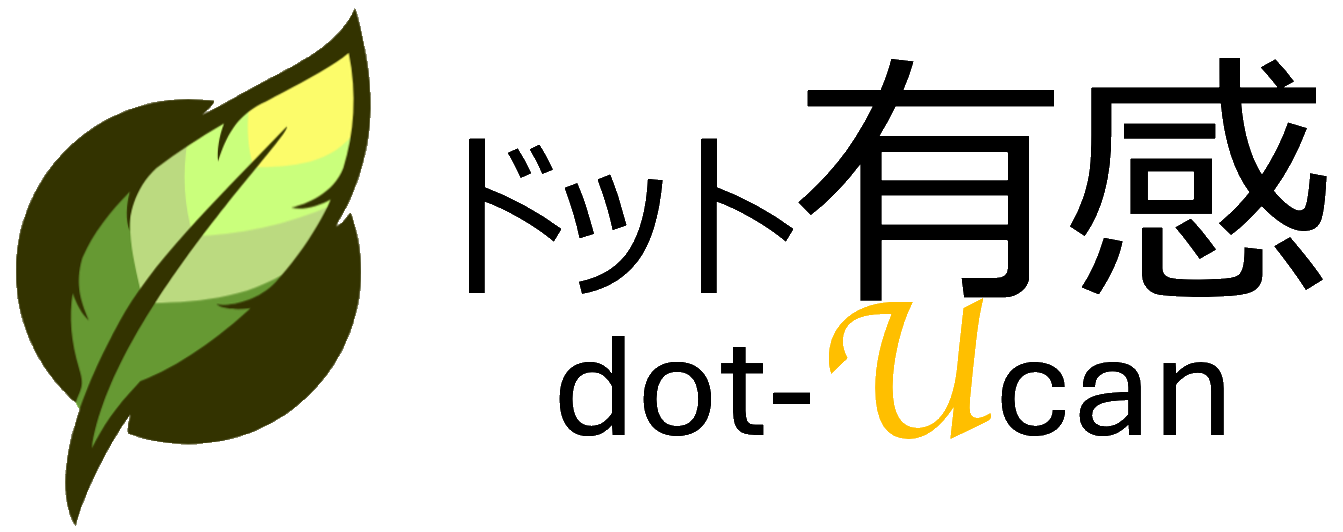
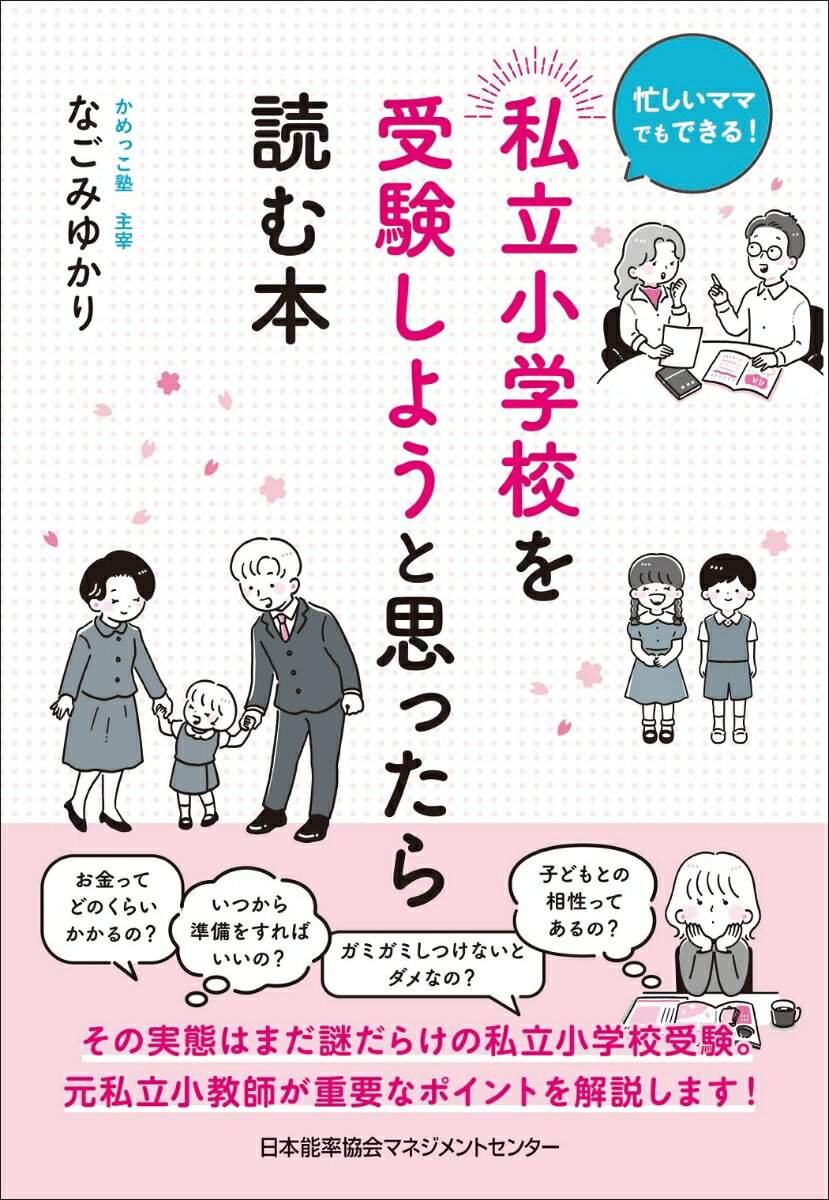
レビュー(6件)
小学校受験を考える時の子どもの年齢はまだ3歳から4歳くらいでしょうか。受験する時は5歳から6歳です。 そんな年齢の子どもに向き合って受験の準備をすることは大変です。 ですが、この本に書いてあることを意識して生活することで、受験だけではなく、基本的な生活を整えることができると思いました。 お受験というと、母親と子どもが頑張っている姿をイメージされる方も多いと思います。しかし両親が仲良く、協力し合うことがとても大事だと著者は伝えています。 そして自分で考え行動できるように日頃から子どもを観察し、うながしていくことも大事な親の役割だということ。 机に座ってする勉強ももちろん必要だと思いますが、色んなことを体験して考える力を養うと、さまざまなシチュエーションに遭遇したときに対応できる力を発揮でき、受験のプレッシャーに負けない子どもが育つのだなと納得しました。
子どもの健やかな成長を願うすべての親へ
著者は、私立小学校の元教師ということもあり、その経験から親と子どもの双方に対して優しい視点でアドバイスをくれ、安心して読めました。 受験対策というよりは、親の心構えや、準備、「受かる子」というのはどんな特徴をもっているかなどが、分かりやすく解説されています。 しかし、受験するしないに関わらず、子どもの健やかな成長を願う方には是非読んでもらいたいです。 マナーやきまりごとを守れる、礼儀正しさを身につける、あいさつできる、座っていられる、あきらめず粘り強く取り組む・・・、これらは小学校という社会生活を送る上で大切なことです。 親はどのような関わり方をしたら子供の成長に貢献できるか、場面別の声かけなどが掲載されており日常生活の中で実践できます。 子どもと一緒に親も挑戦し、より親子の絆を深めたい、そう前向きに思わせてくれる本だと思います。