- 10
- 4.3
謎多き南朝。その実像は、政治・文化的実体をともなった本格政権だった! 大動乱の時代として日本史に深く刻まれた南北朝時代。しかし南朝の実像は謎に包まれてきた。 室町幕府に対し劣勢に立ちながら、吉野山中に長きにわたり存続できたのはなぜか。 厖大な史料を博捜し、政治・文化的実体をもつ本格政権としての南朝に光を当て、 起源である鎌倉時代の大覚寺統から後南朝まで「もうひとつの朝廷」三百年を描き切る決定版。 【本書より】 本書は、こうした南朝研究の課題と研究手法上の特殊性をふまえて、南朝の前史から説き始め、ピークというべき建武の新政、その後身としての南朝をへて、北朝に吸収された後の抵抗運動としての後南朝の段階をふくめた、いわば南朝の全部をひっくるめた総合的な叙述をすることを目指している。そうすることによって、南朝をつらぬく原理というか、真っすぐ通った一本の柱のようなものの存在を明らかにすることができる。 【本書の内容】 第一章 鎌倉時代の大覚寺統 大覚寺統の成立 両統対立の開始 両統対立の展開 両統の相剋 第二章 建武の新政 綸旨万能の成果と限界 軍事指揮と恩賞宛行 王統からみた建武の新政 第三章 南朝の時代 南北朝の併立 後村上天皇の時代 長慶天皇の時代 後亀山天皇と南北朝の合体 第四章 南朝を読みとく 南朝史料としての『新葉和歌集』 南朝の組織と制度 南朝と地方との関係 大覚寺統傍流の末路 第五章 後南朝とその終焉 後南朝の皇胤たち 室町幕府の内紛と後南朝 両統迭立の終焉 ※本書の原本は2005年に講談社選書メチエより刊行されました。
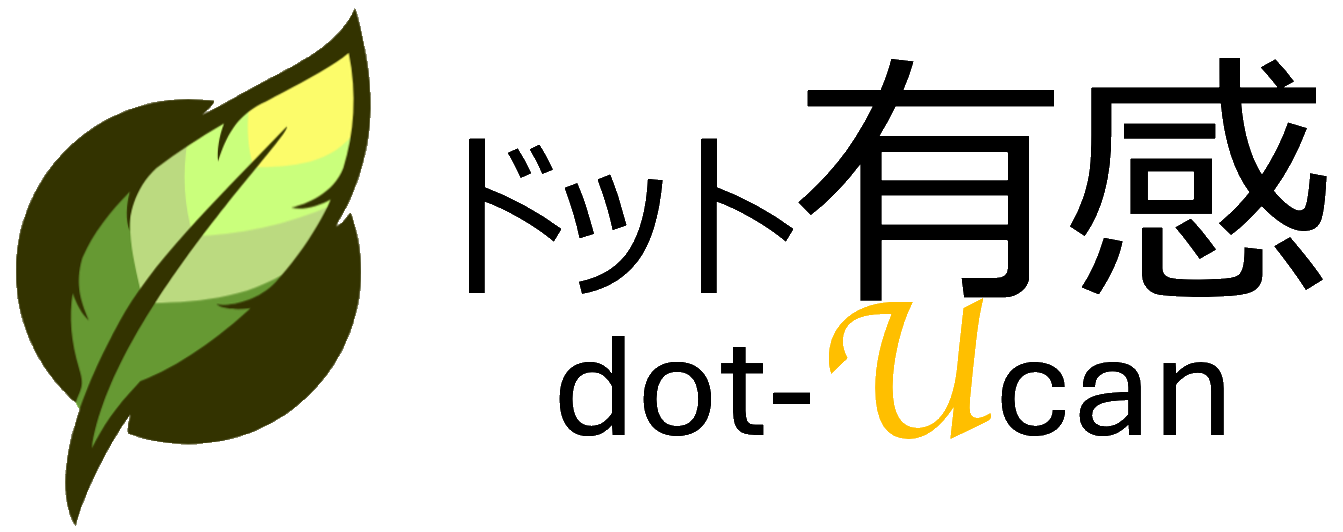
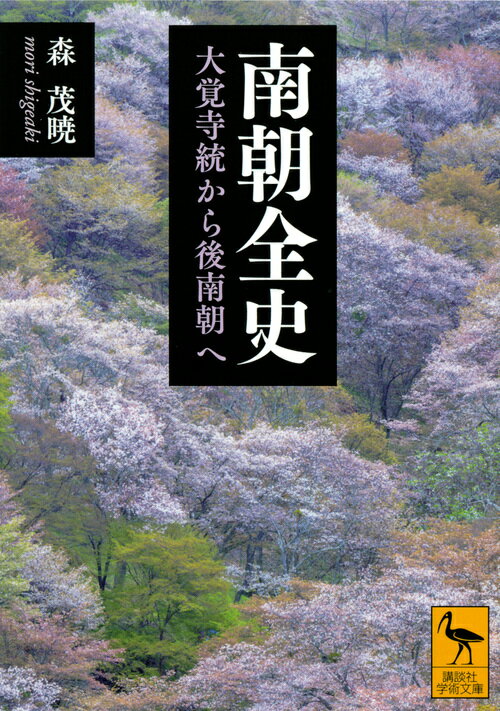
レビュー(10件)
まだ読み始めてばかりですが、南北朝時代に興味があり、マニアックな本ですが購入させていただきました。 楠一族に大変興味があるので、どの程度記述されているのか楽しみです。
新刊の書籍で知りたかった内容が満載なんで喜んでおります。
歴史研究の成果の片鱗から、テーマになっている<南朝>というモノに関して説く一冊だ。読み悪い資料が列記されるというのでもなく、誰でも興味を持って<南朝>というモノのあらましを知ることが叶う好い読物だ。 鎌倉幕府が滅ぼされ、建武新政を経て室町幕府が登場して行くという時期に「南北朝」という“問題”が生じていて、その解決を図るために長い時日を要したこと、その“問題”の故に「南北朝時代」と呼ばれる場合が在る時期が存在することは知られていると思う。で、その“問題”の<南朝>というようなことになると、今一つ巧く説明し悪いような気がする。本書は、それが「もう少しうまく説明出来るように」という内容が紹介されている。 時代毎に差異は大きいのであろうが「皇位継承」の有資格者は限られる。それでもその有資格者が複数在ると、争いめいたことが起こってしまう場合も在る。所謂“中世”の後期、鎌倉時代後半辺りになれば皇位を譲った上皇が「治天の君」として実権を握る“院政”も常態化していた中で、「皇位継承」を巡る諸情勢も煩雑化している。そういう中で、「持明院統」と「大覚寺統」という2つの大きな「皇位継承有資格者」の流れが出て来るのだ。更に「大覚寺統」に関しては“主流”と“傍流”とでも呼ぶべき分裂状態まで生じてしまう。 建武新政を主導したという後醍醐天皇は、「大覚寺統」の“傍流”の出であるという。新政への反発から「持明院統」の<北朝>を擁した勢力が室町幕府を起こし、<南朝>が抵抗して「南北朝時代」という状況が生じている。この状況に関しては、室町幕府の勢威が頂点に達したような、3代将軍であった足利義満の時代に解決が図られたとされている。 実を言えば、足利義満による問題解決以降も<南朝>というモノが絡まる事象は見受けられ、それらは<後南朝>と称される。その<後南朝>は度外視したにしても、<南朝>は何十年も続いていたことになるのだが、「どのように続いた?」という疑問を禁じ得ない。本書は、そういう疑問への回答例を示してくれる。