- 6
- 4.0
「私の生き方ないし考へ方は保守的であるが、自分を保守主義とは考へない。保守主義などといふものはありえない。保守派はその態度によつて人を納得させるべきであつて、イデオロギーによつて承服させるべきではない。」福田恆存が戦後の時流に抗して孤独のなかで掴んだ、「主義」ではなく「態度」としての保守。 時事的な論争家、文芸評論家、脚本家、演出家、シェイクスピア翻訳者など多くの顔を持つ福田恆存は、「保守論客」と位置づけられながらも、その「保守」の内実は、必ずしも十分に理解されてきたとは言い難い。福田恆存にとって「保守」とはいかなるものだったのかーー本書は、その問いに迫るべく、気鋭の若手論客が編んだアンソロジーである。 本書の構成は、以下の通り、1〜5まで、年代順であると同時にテーマ別に構成されているが、福田恆存の思索自体が、問いに対する答えを一つずつ腑に落としながら、時代ごとに形成されたものにほかならないからである。 「1 『私』の限界」〔九十九匹(政治)には回収できない一匹(個人)の孤独とその限界をみつめた論考〕。「2 『私』を超えるもの」〔近代個人主義の限界で、エゴ(部分)を超えるもの(全体)へと開かれていった福田の論考〕。「3 遅れてあること、見とほさないこと」〔近代=個人を超える「全体」を「伝統」として見出しながら、それを「主義」化できないものとして受容しようとした論考〕。「4 近代化への抵抗」〔戦後を風靡した合理主義と近代主義に抵抗した論考〕。「5 生活すること、附合ふこと、味はふこと」〔「生活感情」に基づき、主義ではない、生き方としての「保守」の在り方を示したエッセイ〕。 旧来の「保守」像と「福田恆存」像を刷新する本書は、今日、最良の「福田恆存入門」であると同時に「保守思想入門」である。
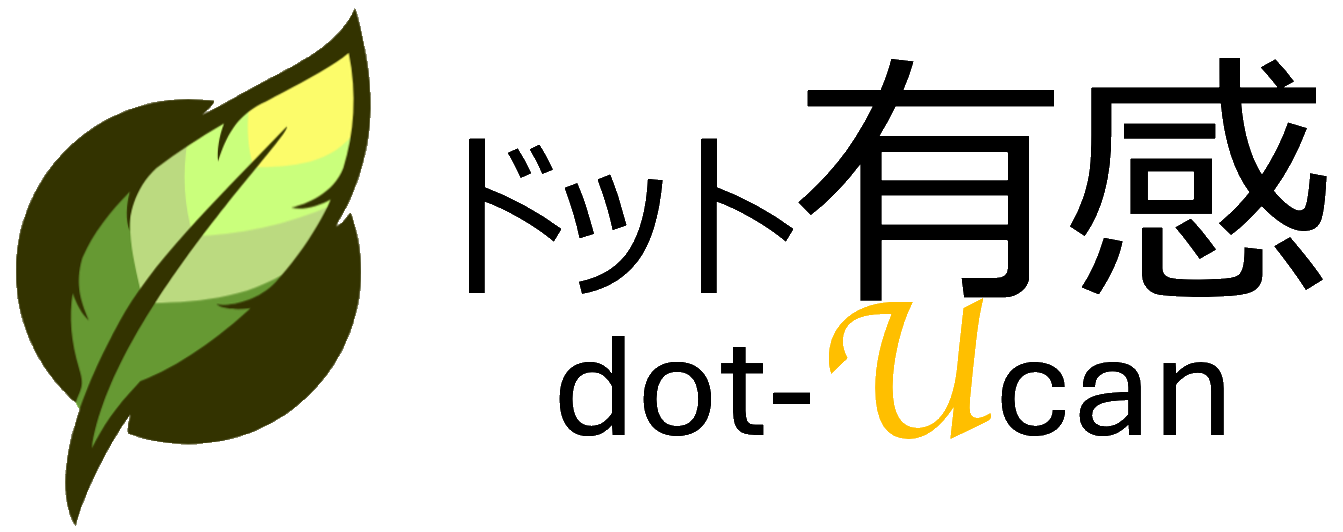
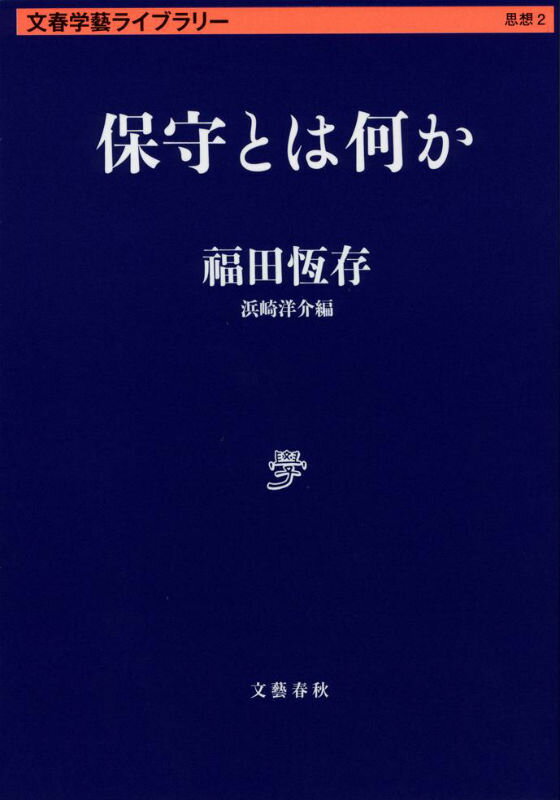
レビュー(6件)
現在福田恆存のような評論家はいるか。
私にとってなかなか難しい本であるが「伝統技術保護に関し首相に訴ふ」のように面と向かって首相に諫言できる評論家は今現在いるのだろうか。また、「保守派は眼前に改革主義の火の手が上がるのを見て始めて自分が保守派であることに気づく。」のだそうである、その通りのように思う。