- 11
- 3.45
関ヶ原の戦い、大坂の陣、 そして日本史上最大級の内戦・島原の乱。 幕府軍12万vs一揆軍3万7000 三人の若きキリシタン侍に待ち受ける試練。 信仰の自由を懸けた最後の戦いが始まる! 歴史小説の第一人者、新たなる代表作! 神とは。信仰とは。生きるとは。 天下分け目の関ヶ原の戦いに西軍で参陣した小西行長の小姓・彦九郎と善大夫、そして肥後の地で守りにつく佐平次。彼らは幼馴染みの若きキリシタン侍だった。敗れて主家を失った三人はそれぞれ全く別の道を歩むことに。やがて、激しい弾圧と苛政に苦しむ島原・天草の民が、奇跡を起こすという四郎という少年の下に起ち上がった。この地で、三人は立場を変え、敵同士となって再会を果たすことにーー。魂震わせる大河巨篇! 【目次】 第一章 生きてこそ 第二章 神はいずこに 第三章 武士と十字架 第四章 運命の変転 第五章 われらの祈りを聞き給え 第六章 讃美歌の海
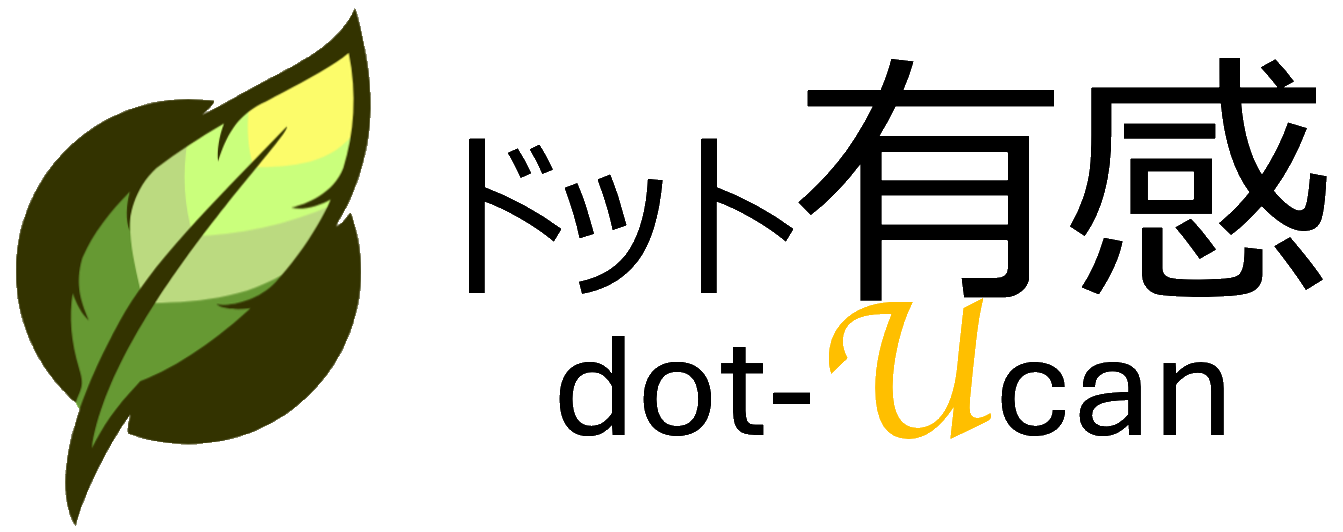
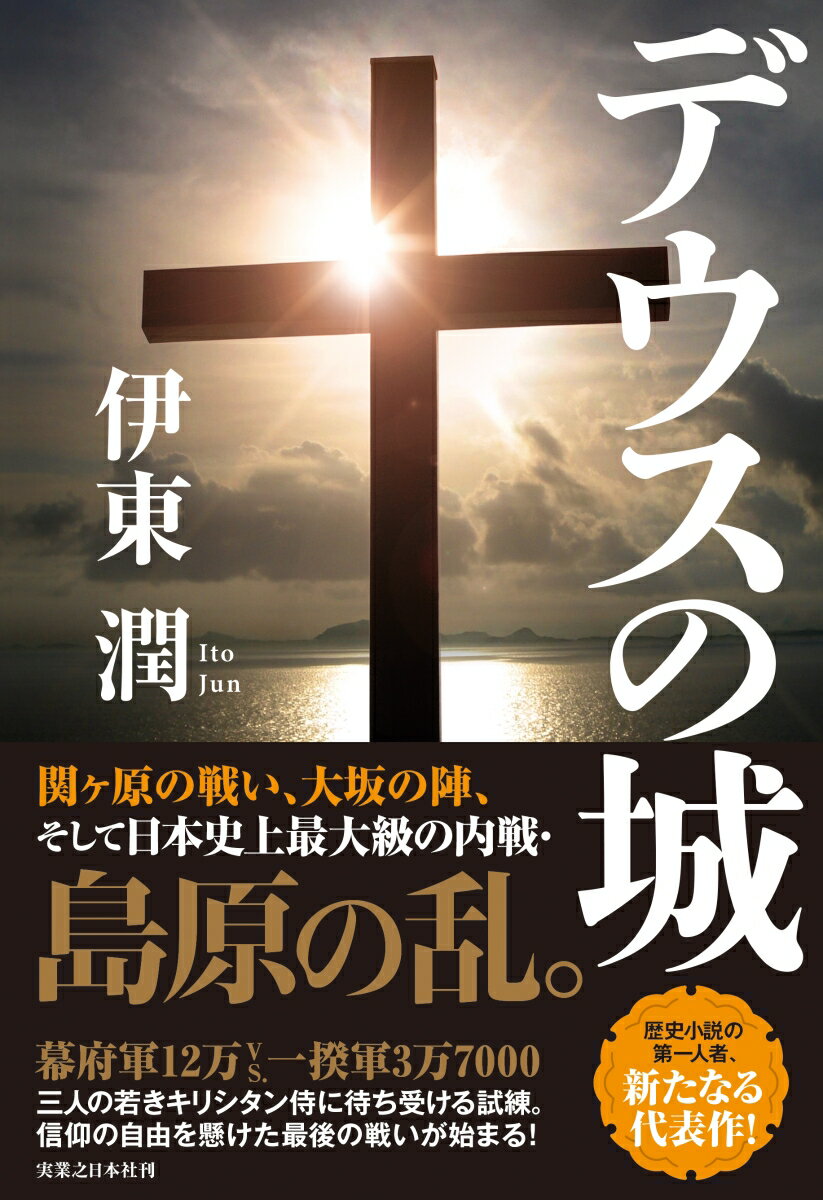
レビュー(11件)
題名に在る“デウス”はキリスト教の神のことで、信者が「キリシタン」という呼び方だった戦国時代や江戸時代に多用されたらしい。そういう話題が出て来る時代モノの小説だが、所謂「時代モノ」を少し突き抜けた、より普遍的な何かを感じた。 同郷である3人の若者達が、揺れ動いた時代の中で各々の路を往くこととなった。やがて3つの路は、長い年月を経て交差することとなる。そういう中で「“信じる何か”と人」、或いは「人としての在り方」というようなことが問われ、各々の路を往く3人の言動がそれを示唆し、読む側に考えさせてくれるというような感じだ。 物語の冒頭、彦九郎と善太夫は関ヶ原に在る。小西行長に仕える小姓として関ヶ原合戦の陣中に在った。他方、左平次は小西家の本拠地である肥後国の宇土城下で、戦時に護りを固めようとしている家中の人達と共に在った。 この冒頭の関ヶ原合戦の頃、3人は15歳だった。この15歳の頃から、50歳代となる島原の乱という頃迄の人生や時代が描かれるのが本作である。 小西行長に従って関ヶ原合戦の戦場を離れた彦九郎、善太夫は、滞在していた村から各々に離れて各々の歩みを始めることになる。左平次は肥後国で自身の人生を拓こうとする。 結局、彦九郎は「イルマン」と呼ばれる修道士になり、善太夫は以心崇伝の下で活動し、左平次は加藤家に仕官する。三人三様の経過、動く時代の中での生き様というのが本作の肝であると思う。 「信じている」に対して「知らない」というのも在る。或いは「信じている別な何か」を重んじようとしている場合も在ろう。そういう時に「知らない」や「別な何か」は排除されなければならないのか?心の中で各々が思う何かを、各々が大切にしていればそれはそれで善いのかもしれない。本作の作中では、こういうような問答のような内容が繰り返されていると思う。そういう様子が、キリシタンの弾圧や、島原の乱のような大事件が起こって行くという中で問われている訳だ。 最近は、より多様な価値観が各々に尊重されるべきであるとするような考え方の他方、或る観方が「正しい」というようなことになると「少し違う」を封じてしまおうとするかのような空気感を感じる場合もないではない。そんな中で、似たような生い立ちの3人が各々に全く異なる路を往く中で、「“信じる何か”と人」、或いは「人としての在り方」を問うような本作は少し沁みた。