- 130
- 3.58
人生の攻略難易度はここまで上がった。 〈きらびやかな世界のなかで、「社会的・経済的に成功し、評判と性愛を獲得する」という困難なゲーム(無理ゲー)をたった一人で攻略しなければならない。これが「自分らしく生きる」リベラルな社会のルールだ〉(本書より) 才能ある者にとってはユートピア、それ以外にとってはディストピア。誰もが「知能と努力」によって成功できるメリトクラシー社会では、知能格差が経済格差に直結する。遺伝ガチャで人生は決まるのか? 絶望の先になにがあるのか? はたして「自由で公正なユートピア」は実現可能なのか──。 13万部を超えるベストセラー『上級国民/下級国民』で現代社会のリアルな分断を描いた著者が、知能格差のタブーに踏み込み、リベラルな社会の「残酷な構造」を解き明かす衝撃作。
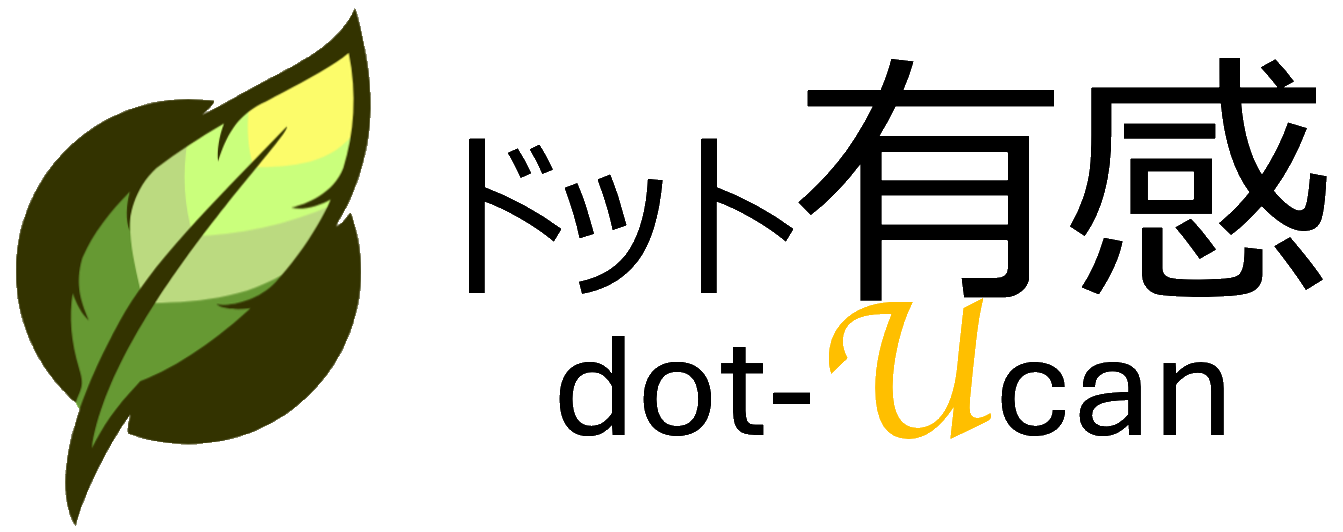
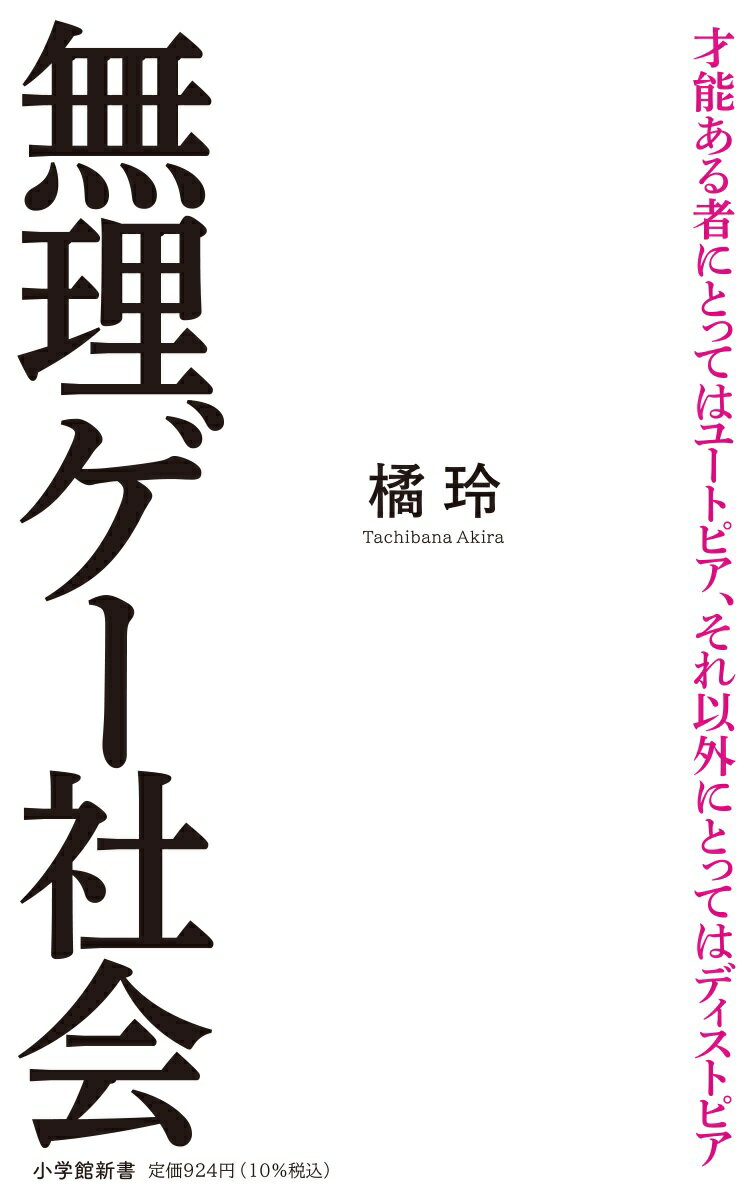
レビュー(130件)
すべて人が当事者である
できればオブラートに包んだまま、ぼんやりとさせておきたかった社会の歪みや人々の心の底にある虚しさがはっきりと、むしろ容赦なく書き記るされている。 国内外の論文やデータから導き出された本文からは薄々気付いてはいたけれど、日々の生活の中で取り立てて口にしなかった、ちよっとした困り事や悲しい出来事ではなく、もはや早急に取り組まざるを得ない具体的な課題であることを思い知らせれた。 このモヤモヤとした不安を解く僅かな希望は、只々真実を深く知ることだけなのかも知れない。
著者は・・
経済が専門なのかな? その流れで、話がそちらの方面に 進んでいくと思います。 その他は、まず、M=I+Eだと言う事。 それは、本書のサブタイトルに合致しています。 次に、ゲシュタルトの祈りは、ずっとインディアンの 言葉だと思っていました。
タイトルが秀逸。戦後が長くなるにつれて格差が広がるのは道理である、とか、リベラルの浸透で下位の男に女性は割り当てられなくなる、とか、ほんと、辛辣で面白かった。
自分の過去を棚卸しをして比較優位を探す
資本主義社会が上流国民と下流国民に分断化され、中間層の多くが下流国民に脱落し、性愛からも排除され遺伝や環境因子によって、下流国民の伽藍から逃れられないと理解しました。ただ、橘氏が以前の著作、「幸福の資本論」で書いているように、幸福は3つの要素で成り立っています。 1.自由 2.自己表現 3.共同体=絆 自由という意味だと非正規社員は経済的自由は制限されていると思います。ただ、残りの2つの自己表現や共同体=絆というのは、マイルドヤンキーという層があるように、お金はないけど地元のイツメンで楽しく支え合いながら生きていくということで、資本を持っており自分の人生の主役になることができると思います。 性愛から除外される=絶望というのもあるとは思いますが、共同体や趣味で自分のキャラ立ちをして、評価(いいね!)を貰えれば、満足度は得られます。もちろん家族と子供に囲まれて、楽しく暮らすのは一つの幸せのカタチだと思います。ただ、現在の限界費用が極端に少ないネット社会では、様々な趣味のニッチが存在し、コストが低いサービスも多いです。企業や社会のコンプラが厳しくなった結果、個人の自由は昔よりあるように思います(定時に帰る、飲み会に行かない、結婚しないなど)。また、結婚しない男女が増えてくれば、お互いに結婚を前提としないマイルドな距離感を持った付き合い方も今後は増えてくるように思います(問題もありそうですが)。 もちろん経済的自由を達成できる人は達成して、幸せを得ることもできます。共同体で評判をとって生きる事もできます。もちろん、最低限の金は必要ですが日本のデフレが今後も続くことが予想され、社会の弱者に回ることによって、政府の支援を最大限に享受することもできます。 何れにせよ、自分の性格や能力、個性は遺伝によって半分が決められ、自分で自助努力できる部分は限られています。その条件下で自分の能力・性格の棚卸しをしてキャラ立ちをした人生が送れれば、人生の勝ち組だと思います。 絶望感を味わう前に、自分の過去の歴史を振り返って、何が楽しかった、できたかの比較優位(他社との絶対比較ではなく、自分の能力・興味の優位性)を見つけて、そこに一点集中で生きていくことが、自分が人生の主人公になれる鍵だと思いました。 村上春樹の小説のダンスダンスを思い出しました。 自分が一番うまく踊