- 119
- 3.7
メディアアーティスト、筑波大学准教授、ベンチャー企業の代表など多彩に活躍する著者。時代の先端を行く著者の思考の源は、実は読書で培われたという。それは、読んだ内容を血肉にするための「忘れる読書」だ。デジタル時代に「持続可能な教養」を身につけるために必要なのは読書だと、著者は断言する。 本書では、古典から哲学、経済書、理工書、文学に至るまで、著者の思考を形作った書籍を多数紹介し、その内容や読み解き方を詳説。著者独自の読書法はもちろん、本の読み解きを通して現代社会を生き抜く思考法までが学べる、知的興奮に溢れる一冊。 【目次より】第1章 持続可能な教養ーー新しい時代の読書法/第2章 忘れるために、本を読む/第3章 本で思考のフレームを磨け/第4章 「較べ読み」で捉えるテクノロジーと世界/第5章 「日本」と我々を更新(アップデート)する読書/第6章 感性を磨く読書/第7章 読書で自分の「熱」を探せ
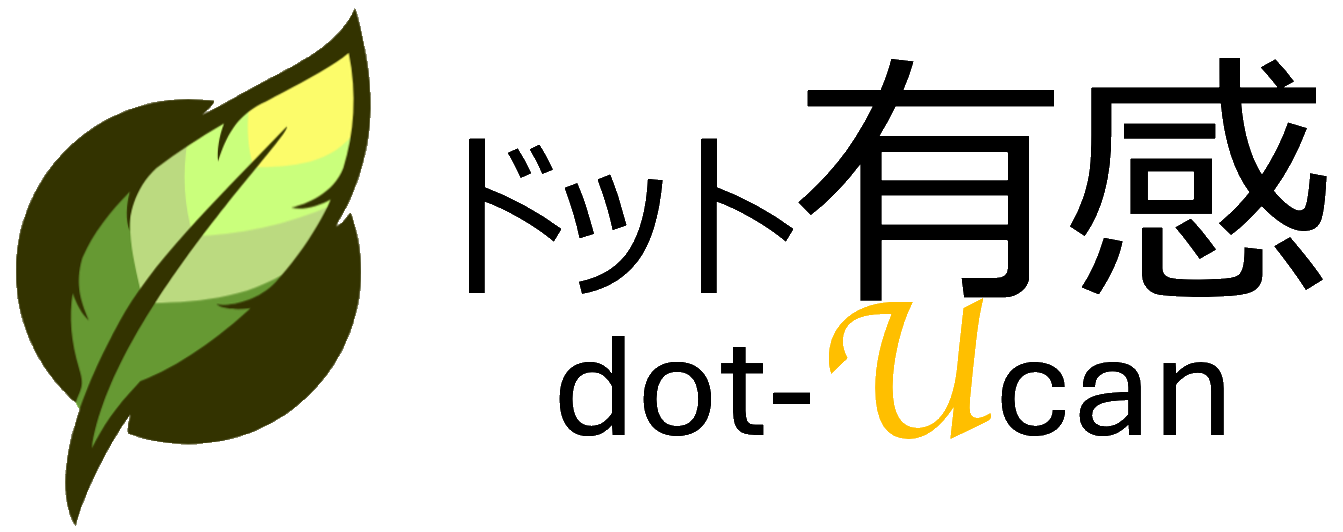

レビュー(119件)
何でも検索できる世の中で、情報を持っていること自体の価値は低下した。そんな中で価値を生み出すのは、自分なりの「文脈」に気づき、俯瞰して情報を位置づけられる人であるという。先行きのわからない時代に必要な教養を「持続可能な教養」として、➀物事を「抽象化する思考」を鍛えること➁「気づく」能力を磨くことという。そんな力をつけるのに読書は最適。忘れる読書とは、自分なりの文脈に本の内容を位置づけ、点と点を結んでいく読書。著者が読んでいる本の幅広さを見ると、著者の発想の深さ、広さがわかる。そして読みたい本がまた増えた。
忘れるという発想が面白いが、結果として読書すればするほど知識は上がるのかと思います。
出てくる本がやはり知識人の方はこういうのを読むんだなぁとしみじみ知ることができました。 凡人にはなかなか真似できない発想なのかと思いました。