- 10
- 4.29
「自分を曲げず、それでいてみんなとより良くやっていける方法」 多様性社会にこれから必要なリーダーシップのあり方とは、一人ひとりの個性を伸ばし、能力を引き出してチームで最大の成果を上げられることではないでしょうか。共感力が高く、かつ周りの意見に流されないEQ(心の知能指数)の高いリーダーが、多様性ある組織で新たな価値を生み出せるのです。 2023年HPワークリレーションシップ・インデックスによると、66%の人が「EQの高い上司の下で働くためなら給与減を喜んで受け入れる」と回答しているほど、ビジネスの場で重要視されています。 著者の近藤弥生子さんは台湾に10年以上在住し、オードリー・タン氏をはじめ台湾のリーダーたちのEQの高さを目の当たりにしたといいます。 本書では、『「静かな人」の戦略書』の著者で、台湾在住のジル・チャン氏の協力を得て、改めて現代に必要な高EQの人とはどのような人なのか、どのような考え方や振る舞いをするのかを検証しました。IQ(知能指数)は生まれた時にある程度決まっているのに対し、EQは自分自身で育てることができる能力です。自分を曲げず、感情に振り回されることなく他の人たちともより良くやっていける高EQリーダーを目指してみませんか。 はじめに 第1章 今、EQが必要とされる理由 なぜ日本人は「高IQ」「天才」といった言葉に弱いのか? 台湾で高EQのリーダーが評価されるワケ 第2章 台湾式EQをひもといてみよう 日本人の「空気を読む」力とは何が違うのか 台湾人作家、ジル・チャンさんとEQ談議 ジルさんが考える「高EQな人物像」 台湾式のEQが日本に通じる理由 台湾で「高EQ」「低EQ」とされる人物とは 第3章 ジル・チャン氏に教わる、高EQ戦略 実践編 1 周囲からの期待に対する悩み 2 上司とのコミュニケーションについての悩み 3 立場の違う同僚に対する悩み1 4 立場の違う同僚に対する悩み2 5 受け身な部下に対する悩み 6 文句が多く働かない年上の部下に対する悩み 第4章 「台湾式EQ」チェックシート 台湾式EQを構成する5つの要素 あなたのEQチェックシート 第5章 イラッ・モヤッとした時に思い出したい、台湾の言葉たち
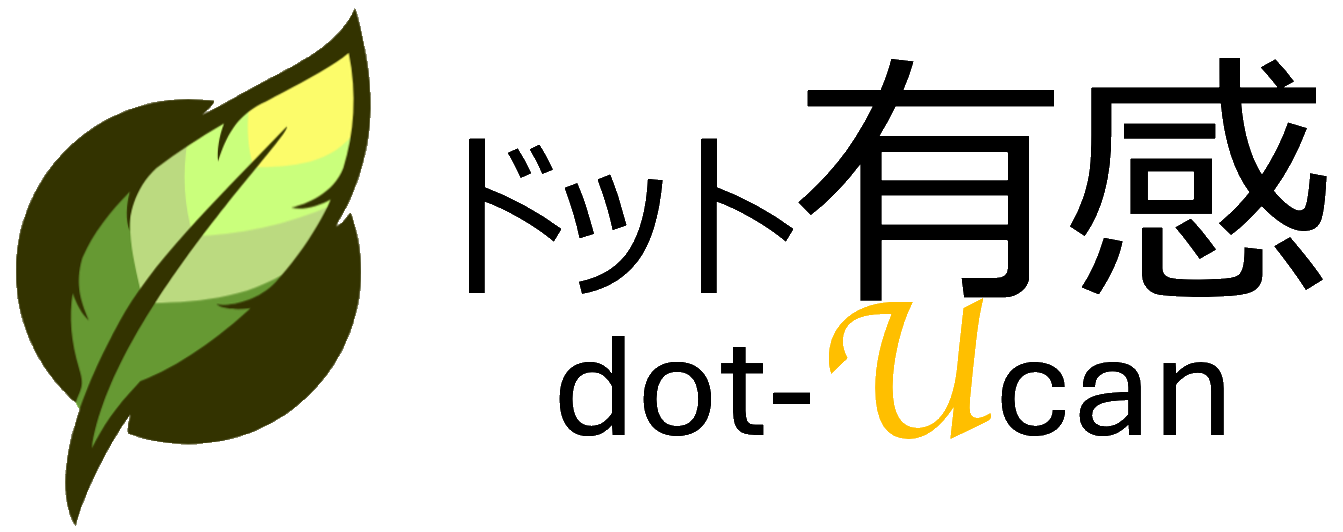
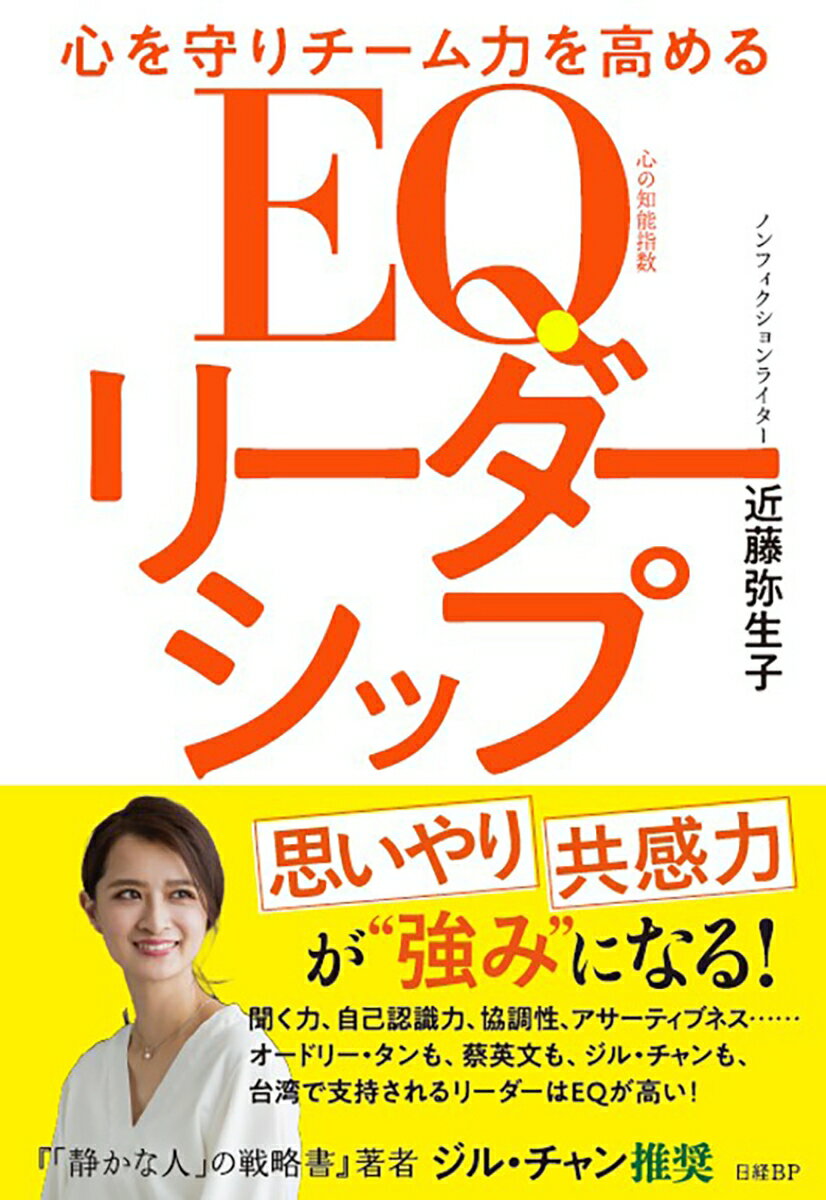
レビュー(10件)
EQは今の日本に必要な概念
多様化する社会に適応しきれない今の日本人に必要なのが、このEQという概念だと思う。 自分を曲げず、それでいてみんなとよりよくやっていける方法を見つけ出す。1か0でない、賛成か反対でない、第3の案である。合理的で実を取る台湾の人々は、これがとてもうまいようである。 また、日本では怒りをあらわにし、人を動かそうとすることが、普通のことになっているが、世界から見ると普通のことではない。そういう人は白い目で見られ、相手にされない。 不機嫌オーラを出したって、怒鳴り散らしたって問題は解決しない。大切なのはEQを発揮して、双方によりよい方法を考え出すこと。感情的な自分には難しいが、EQ高い人ならどうするだろう?と一度立ち止まって考えるようにしたい。
自分を犠牲にせず、人も困らせない
近藤弥生子さんが台湾に住んでいて、少しずつ楽になって行った過程に、台湾のEQの高い人たちの存在があったと伝わってきます。 台湾EQ本。 アメリカから来たEQ本を読んだことがある人も、全く知らなかった人も、まずは“第3章”の #ジルチャン 氏に教わる高EQ戦略 を読んで欲しい。 具体的な悩みに対する答え、と言う形式でEQが高い、とはどう言うことなのかが理解しやすくなっている。 自分に、あるいは周りにとって必要な内容だと理解してから読むと、「簡単だけど、難しいこと」が身体中を巡るように入ってきます。