- 20
- 3.89
過去の景観の残片は、さまざまな形で地図に姿を留めている。地名や地形、道路、寺社などの位置関係と実地の検分から、そこに生きた人々の「地表経営」とその意図を解明する<歴史地理学>の楽しみ。聖武天皇の都・恭仁京の全貌、信長の城地選定基準、江戸建設と富士山の関係など、通常の歴史学ではアプローチできない日本史の側面に新たな光をあてる。 原本は、『景観から歴史を読むー地図を解く楽しみ』(1998年、日本放送出版協会刊) 序章 地図と地名に残された先人のシグナル 第1章 聖武天皇の都作り 第2章 平安京計画と四神の配置 第3章 古代地方行政の中心地、国府 第4章 古代の大道は直線であった 第5章 条里 第6章 荘園の範囲を確定する手順 第7章 織田信長の城地選定構想を読む 第8章 天下の大道と隠れ道の並走 第9章 豊臣秀吉の「首都」作り 1 第10章 豊臣秀吉の「首都」作り 2 第11章 徳川家康の江戸選地理由 第12章 「野」とは何か 第13章 溜池分布の謎を解く 第14章 新しい地名解釈から見えるもの 第15章 耳納山・伊吹山・浅間山 第16章 小字「心蓮寺」が発信した情報 第17章 都市内道路名称の意味を解く
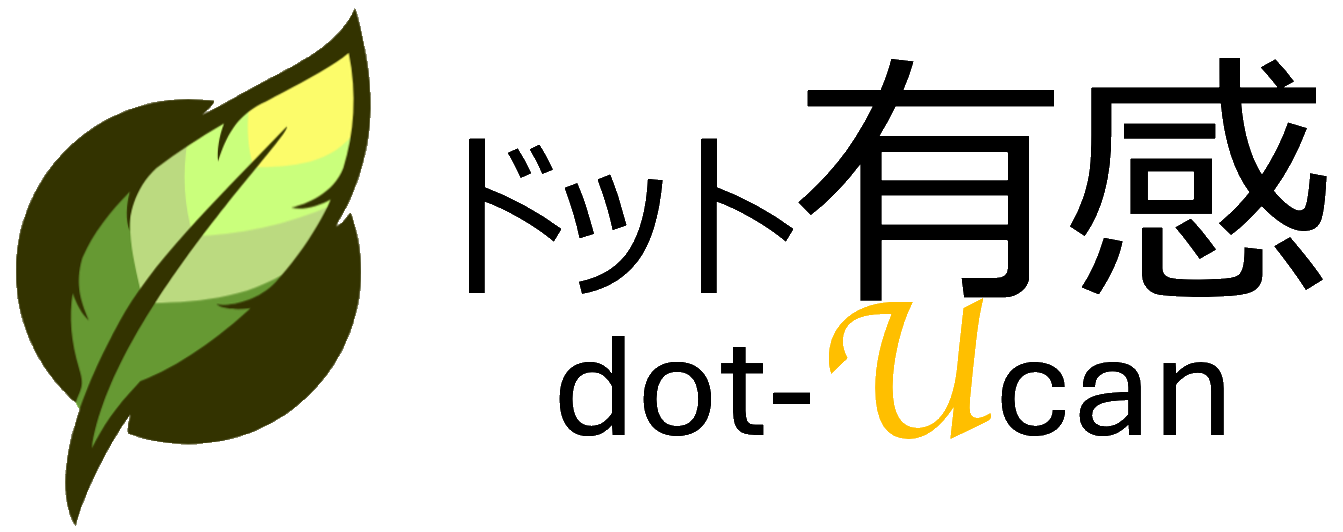
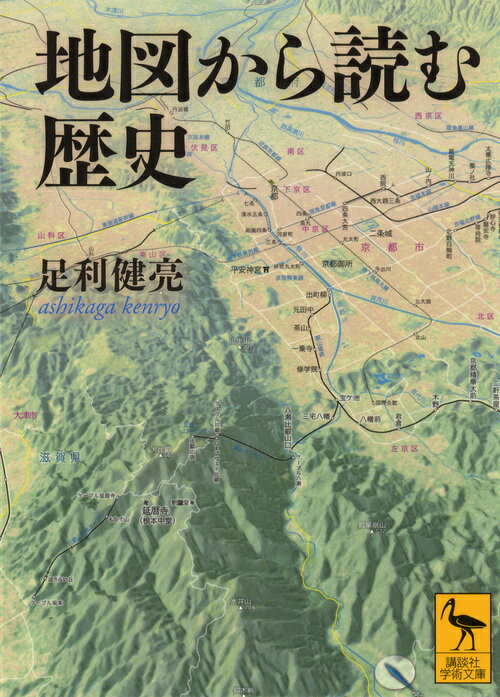
レビュー(20件)
ちょっと難解だが、興味深い本
「この地域は昔はどういう感じだったのだろう…」という興味がふつふつと湧くきっかけとなる本でした!仕事柄、電車での移動が多い性質ですが、移動中の車窓を一味も二味も豊かにしてくれる本でもあります。
地図に関する歴史を勉強するため購入しました。興味深い部分もあり勉強になります。
地形好きの人にはたまらなく面白い
地形と地名などが関連しているのは当たり前だが、そこに歴史があることを読むたびに納得させられる面白い本です
かなり専門的だが面白い
地図から歴史を読む本は他にもあると思いますが、これはかなり専門的。歴史散歩の好きな同僚の勧めで購入しましたが、本文を読みながら図や古地図を何度もチェックして読み返しながらでないと、ついて行けません。現存する地形から古代を読み解くという意味でとても興味深いものです。